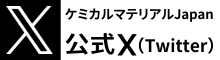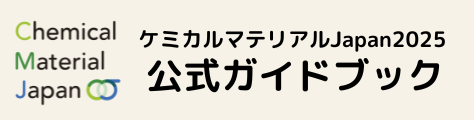基調講演
(2025年)
基調講演会場A・B:定員各200名
聴講には事前申込が必要です。
定員に達した場合、キャンセル待ちはございません。
お席に余裕がある場合は、当日聴講が可能です。
当日聴講分に関しては、前講演の入場終了後から講演会場前にて待機列を準備しますので、係の指示に従ってお並びください。
本講演は資料配布およびオンラインでのライブ・アーカイブ配信は予定しておりません。
先端化学材料・素材総合展
富士フイルムの変革と挑戦

KA1-111月27日 10:30~11:10 [基調講演会場A]※本講演前に開会式を行います。10:20までにご着席ください。
富士フイルムホールディングス株式会社
代表取締役社長・CEO 後藤 禎一
富士フイルムグループは「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」というグループパーパスのもと、社会課題の解決に貢献する価値提供を通じて、笑顔あふれる未来に向けた挑戦を続けています。本講演では、富士フイルムグループの90 年以上にわたる挑戦と変革の歴史を振り返るとともに、事業ポートフォリオの多角化とイノベーションを軸にした成長戦略をご紹介します。
シンガポールのE&Cビジョンと戦略

KA1-211月27日 11:40~12:10 [基調講演会場A]日本語講演
EDB(シンガポール経済開発庁)
シニアバイスプレジデント兼国際業務責任者(日本・韓国担当)
チュア・イァクフア・クラレンス
シンガポール経済開発庁は、シンガポールのエネルギー・化学産業の概要を共有し、現在の状況、成長のための主要な戦略、日本のカウンターパートとのパートナーシップの機会を網羅します。
成長軌道への回帰〜住友化学の新成長戦略

KA1-311月27日 13:00~13:30 [基調講演会場A]
住友化学株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 水戸 信彰
当社は、社会が直面する課題に対し、革新的な製品や技術によるソリューションを提供する「Innovative Solution Provider」を目指しています。本講演では、その第一歩として、「Leap Beyond~成長軌道への回帰~」を掲げ、2025年度からスタートした中期経営計画で推進している「新成長戦略による事業ポートフォリオ高度化」「構造改革の継続的な遂行による強靭化」などの、成長軌道への回帰と持続的な成長に向けた取り組みをご紹介します。
半導体リレーセッション:半導体業界における技術戦略と未来展望

KA1-411月27日 14:20~15:50 [基調講演会場A]
東京応化工業株式会社 先端材料開発一部 部長 小室 嘉崇
本講演では、東京応化工業株式会社のEUVレジスト技術の紹介をします。高感度、高いパターニング性能を有するEUV露光向けのフォトレジストについて技術的な観点から発表を行います。
エーエスエムエル・ジャパン株式会社 Corporate Marketing テクニカルマーケティングディレクター 永原 誠司
半導体製造の微細化を支えるリソグラフィ技術は、EUV・DUV露光技術、計測・計算リソグラフィの進化により、高精度・高効率なパターニングを実現しています。本講演では、露光・検査・計算リソグラフィの統合による次世代ノード対応の技術的課題と解決策を紹介します。将来のリソグラフィ関連材料への期待についても議論します。
Rapidus株式会社 エンジニアリングセンター フェロー 野中 敏央
AI活用の進展からの要求計算量の増大が急速である。これに応えるためハードウェアとして1パッケージ内のロジックのトラジスタ数、メモリ容量を増やす必要がある。この要求のスピードが高く、テクノロジーノードの進展への依存では賄いきれなくなっており、SiインターポーザーやRDLインターポーザー上で複数のロジックチップ、HBMをインテグレーションする技術の開発が急速に進んでいる。本講演ではこれらの技術について紹介する。
日本の化学業界の課題と中期展望

KA1-511月27日 16:20~16:50 [基調講演会場A]
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
株式統括本部 副本部長 マネージングディレクター 渡部 貴人
アジアの石油化学業界に光明が差しつつある。中国の反内巻政策(Anti-involution)、韓国におけるナフサクラッカー設備縮小といった構造改革により、アジア石化需給は中期的に改善に向かう。一方、TOPIX化学株指数は依然として市場平均を下回る状況が続く。収益性や効率性(ROE)の低さが最大の理由である。本セッションでは、日本の化学業界の課題整理に加え、中期展望について論じる。
素材産業の国際競争力強化に向けた産業政策

KA2-111月28日 10:30~11:00 [基調講演会場A]
経済産業省
製造産業局 素材産業課長 土屋 博史
今後、素材産業がカーボンニュートラルを目指しつつ、多様な変革の要請に的確に対応し、今後も国際競争力を維持・強化していくためにどのような取組が必要か、今後の素材産業の方向性について、GXの政策動向とともにご紹介。
化学産業とサステナビリティ~グローバルな国と産業の競争の中で

KA2-211月28日 11:30~12:00 [基調講演会場A]
三菱ケミカルグループ株式会社
執行役員 チーフサステナビリティオフィサー 三田 紀之
カーボンニュートラル(CN)やサーキュラーエコノミー(CE)は、厳しい構造的な国際競争の中で、日本の化学産業が生き残っていくための新たな価値となる。欧州や米国での規制や支援が大きく左右するなど、短中期的には規制政策や市場動向に不透明な部分もあるが、グローバルな議論を踏まえ、長期的視野で日本の化学産業としてサステナビリティにどう対応し国際競争力を高めていくか、その対応の方向性と課題について紹介する。
「京葉臨海コンビナートのカーボンニュートラル推進に向けて」
―産官学金による地域連携と未来へのロードマップ―

KA2-311月28日 13:00~14:50 [基調講演会場A]
温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすることを目指して、世界中で技術、政策、地域連携など多角的な取り組みが加速している。なかでも、ものづくりにおけるネットゼロの実現が最もハードルが高い。一方、世界に先駆けてHard to Abate産業のネットゼロを実現することで、競争力の源泉として、強いものづくりの再興の実現につなげることができる。本セッションでは、日本の産業を支える重要な拠点である京葉臨海コンビナートを事例に、技術、経済性、社会の仕組みに関する課題、および各ステークホルダーへの具体的要望について議論する。
東京大学 環境安全研究センター 教授/ 化学工学会 地域連携カーボンニュートラル推進委員会 委員長 辻 佳子
市原市長 小出 譲治
出光興産株式会社 執行役員 CNX戦略部長 田中 洋志
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス/株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員 宮地 信幸
千葉銀行 取締役専務執行役員 グループCSuO 淡路 睦
世界初「実用発電」可能な核融合炉とフュージョンエネルギー産業

KA2-511月28日 16:20~16:50 [基調講演会場A]
株式会社Helical Fusion
共同創業者 代表取締役CEO 田口 昂哉
太陽の輝きを地上で再現するフュージョン(核融合)エネルギーは、火力や原子力等のベースロード電源を代替しうる効率性を持ち、CO2フリーで燃料枯渇の心配がなく、安全性も確保しやすい究極のエネルギーです。常時安定的に電力を供給する「実用発電」可能なプラントができれば、数百兆円規模の産業を創出できる可能性があります。フュージョンエネルギー産業実現の見通し、それを支えるサプライチェーンの重要性を紹介します。
中国台頭時代に挑む日系化学の未来戦略

KB2-411月28日 13:30~14:00 [基調講演会場B]
アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部 ストラテジーグループ 化学・素材/天然資源 プラクティス日本統括
マネジング・ディレクター 安田 信太郎
中国化学企業の国家的投資拡大や米中対立に伴う国際環境の変化は、日本の化学産業に競争力再構築を求めています。本講演では、中国企業の戦略と世界市場への影響を整理し、欧米企業の積極的対応策も踏まえながら、日本企業がグローバル市場で競争優位を確立し持続的成長を実現するための戦略オプションを提示します。
中国BYD/吉利/小米等中国OEMの競争力

KB2-511月28日 14:30~15:00 [基調講演会場B]
株式会社フォーイン
取締役 中国調査部 部長 周 錦程
世界OEMが中国のOEMを脅威と感じる理由を深掘りし、具体的な事例を通じてその実力を明らかにします。例えば、BYDの低コスト要因や、吉利のブランド統合戦略、小米のデジタル技術の進展等が挙げられます。また、中国政府の支援が各社の成長を後押ししている点にも触れ、今後の競争環境と市場展望についても分析します。
国内自動車産業の現状課題と、今後国際競争力を獲得する戦略

KB2-611月28日 15:30~16:15 [基調講演会場B]
名古屋大学 モビリティ社会研究所
客員教授 野辺 継男
世界EV市場は今年2000万台超へ拡大する一方、日本市場は約10万台規模で停滞し、技術ギャップが拡大している。国際的に売れるEVはSDV化が前提となり、これを支えるE/E (電気/電子)アーキテクチャの中央演算+ゾーン化や、電池など電気化学の進化が加速し、自動車産業の変革が進んでいる。背景として半導体と生成AIの指数的成長も関係する。本講演では現状を俯瞰し、産業構造と開発体制の刷新による国際競争力回復の道筋を示す。
化学物質管理ミーティング
先端PFAS類の分解・リサイクル技術の研究動向

KA2-411月28日 15:20~15:50 [基調講演会場A]
神奈川大学
理学部 教授 堀 久男
近年、PFASと呼ばれる化合物の範囲が、有害性の有無を問わず拡大しています。フッ素ポリマーも含めたPFASには、カーボンニュートラルの社会や高度情報化社会の実現に不可欠なものも多数あります。化学物質の問題は化学の技術で解決しなくてはなりません。本講演では現在、さらに将来においても産業界にとって重要な「先端PFAS類」を対象とした分解・再資源化方法について、世界の研究状況を解説します。
経済産業省における化学物質管理政策の最新の動向について

KB1-111月27日 10:40~11:10 [基調講演会場B]
経済産業省
産業保安・安全グループ 化学物質管理課長 大本 治康
経済産業省が担当している化学物質管理政策のうち、化審法、化管法、オゾン法、フロン法、化兵法及び水銀法を中心に、政策の概要及び最新の動向等について紹介する。
GFC国内実施計画の策定と環境省の化学物質管理政策について

KB1-311月27日 12:35~13:05 [基調講演会場B]
環境省
大臣官房 環境保健部 化学物質安全課長 塚田 源一郎
2023年9月、多様な部門の多様な主体によるライフサイクル全体を対象とする包括的な化学物質管理の国際枠組みである「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)」が採択された。これを受け、我が国では、関係省庁連絡会議における議論、国内の各実施主体との対話等を行った上で、2025年4月にGFC国内実施計画を策定、公表した。本講演では、GFC国内実施計画と環境省における化学物質管理政策について紹介する。
職場の化学物質管理に関する厚生労働省の取組み

KB2-111月28日 10:30~11:00 [基調講演会場B]
厚生労働省
労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課長 中野 響
国は、事業者が、化学物質の危険性・有害性の情報に基づきリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、ばく露防止のために必要な措置を実施する自律的な管理を推進している。こうしたなか、今年5月には労働安全衛生法等の一部を改正する法律が公布された。その内容を含め、最近の化学物質管理の動向を紹介する。
プロセス産業DX展
未来を共に創る:旭化成の無形資産とデジタルの可能性

KB1-211月27日 11:40~12:10 [基調講演会場B]
旭化成株式会社
取締役 副社長執行役員 研究開発・DX・知的財産統括 久世 和資
旭化成は、DXと知財を軸に、無形資産を最大限活用した価値創造に挑戦しています。本講演では、マテリアル・住宅・ヘルスケアなど多様な事業領域での無形資産経営の実践と、ソリューション型・IPアセット型事業への展開、生成AIやデジタル人材育成による競争力強化の取り組みを、具体的な事例とともに紹介します。
松尾研発スタートアップ 製造業における生成AI活用最前線

KB1-411月27日 13:30~14:00 [基調講演会場B]
株式会社エムニ
代表取締役 下野 祐太
製造業に特化してAIシステム開発を手掛ける松尾研発/京大発スタートアップエムニが化学業界における最先端の生成AI活用事例を4つご紹介させていただきます。
1. 保全業務における見積仕様書作成業務の省人化エージェント
2. 暗黙知の言語化・技能伝承を実現するAIインタビュアー
3. 「経営に知財を」を実現するAI特許ロケット
4. マテリアル・インフォマティクス領域における生成AI活用事例
AI・DXが拓く日本の製造業の未来〜政府のビジョンと産業界の共創による競争力強化〜

KB2-211月28日 11:30~12:00 [基調講演会場B]
経済産業省
製造産業局 総務課 製造産業DX政策企画調整官/AIロボティクス推進官 産業機械課長 須賀 千鶴
AI・DXによる製造業の未来を展望し、政府が推進する産学官連携やルール整備の方向性を紹介。また、アナログ規制の見直しやデジタル技術の社会実装に向けた官民の取組を通じて、日本の産業競争力強化に向けた事例を説明。
NGK グループにおける DX 推進の取り組みと人材育成

KB2-311月28日 12:30~13:00 [基調講演会場B]
日本ガイシ株式会社
技術統括、研究開発本部・製造技術本部・安全品質環境統括部・知財戦略部・デジタル変革推進部・ICT センター所管
取締役専務執行役員 森 潤
日本ガイシは 2021 年に「NGK グループビジョン Road to 2050」にてありたい姿を掲げ、その達成に向けたなすべきこととして、ESG 経営・収益力向上・研究開発・商品開花・DX の5つの変革を定め、DX をこれら全体の推力としました。本講演では、研究開発における DX 推進と、変革の中心となる“人”の育成の取り組みを中心に紹介します。
産業安全フォーラム
パネルディスカッション:化学プラントの人材確保と育成~安全維持のための未来戦略~

KB1-511月27日 14:50~16:50 [基調講演会場B]
製造業でも人の採用は難しくなり若手の離職率も増加して人材確保は重大な問題になってきた。更に経験豊富な人材の減少も相まって、これまでの様な人に頼るオペレーションは出来なくなると思われる。石油・化学業界の実態把握を行い課題が明らかになった。プラントの安定運転や安全を維持していくためにどのように人材を確保し、育成していくのか。DX等の技術活用を行っていけばいいのか議論し、対策を一緒に考えていきたい。
特定非営利活動法人 保安力向上センター 会長 松尾 英喜
東京農工大学 工学部 名誉教授 山下 善之
住友化学株式会社 生産技術、生産安全基盤センター、エンジニアリング、レスポンシブルケア統括
常務執行役員 荻野 耕一
AGC株式会社 技術アドバイザー 井上 滋邦